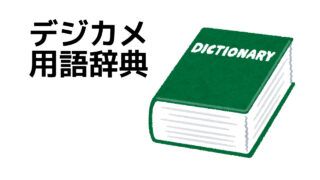レンズの口径食とは
口径食とは写真の四隅が暗くなってしまう現象のことで、これはレンズを通った光の量が、中央部と周辺部で違うことから発生してしまう現象です。
レンズに入ってくる光は常に平行ではなく、斜めからも光が入ってきます、斜めから入ってきた光は光量が低下するため、写真の四隅が暗く写ってしまいます。これを周辺光量の低下ともいいます。
これは青空など明るい場所を撮影し、絞りを開放で撮影した時に強く現れます。


ラップやトイレットペーパーなどの筒で景色をのぞき込んでみたとき、真正面から見ればちゃんと丸い景色が映ると思いますが、ちょっと見る位置を変えると、景色がラグビーボールやレモンみたいな形に見えますよね。更に見る角度を変えるとやがて筒の中の壁しか見えなくなります。
せっかく綺麗なたまボケを作ろうと思っていたのに、なぜが玉にならずレモンみたいな点光源ボケが発生するのも、同じように口径食が原因です。
筒から見える穴を小さくすれば、少々筒から見る角度を変えても丸く見えますね、これと同じことで絞りを絞ってやることで、口径食は軽減できます。
特に美しい玉ボケの場合は、絞りすぎるとボケないですし、開放しすぎると綺麗な玉にならないので、絞りを変えながら何度か撮ってみて綺麗に玉になる所を探してみるといいですね。
レンズの性能によっても変わってくるので、周辺光量の低下は絞りを絞っても軽減しない場合もあります。そのような場合はソフトで強制的に周辺の明るさを上げる方法もあります。